※ こんにちは、当ブログの管理人です。当ブログではアフィリエイト広告を利用しております。
それではごゆっくりとご覧ください。
レシピと作り方
材 料

Recipe no.089
- カンパリ・・・・・・・・・・・30ml
- スイートベルモット・・・・・・30ml
- ソーダ・・・・・・・・・・・・Full
- レモンスライス
※ Full = グラスの8割~9割まで満たす適量のこと
技法 = ステア
- このカクテルの〚 材料リスト 〛へ ⇓
作り方
グラスは、炭酸が抜けにくい コリンズグラス をお勧めします。 他にも ゴブレット、タンブラーグラス などが使われていることもあります。

グラスにカンパリ、スイートベルモットを入れ ステア をし、氷を入れます。
泡立たないように静かにソーダを満たし、ゆっくりと軽くステアをします。
炭酸類を混ぜる場合は、ゆっくりと1~2回転ステアし、氷を上げ下げすれば混ざります。
準備しておいたレモンスライスを、バースプーンで押し込むようにグラスの中に入れて完成です。
- このカクテルの〚 道具リスト 〛へ ⇓
アメリカーノの特徴

イタリアを代表するハーブ&ビター系リキュールのカンパリの苦味と香りに、甘味とハーブの香りが特徴のスイートベルモットをソーダで割ったカクテルです。 飲みやすさ、飽きの無さ、サッパリ感から、食前酒( プレディナーカクテル )として飲むこともお勧めできます。アメリカーノはその名の通りイタリア語の名前で、イタリア産の材料をアメリカンスタイルにしたカクテルです。
アメリカーノは、1920年代から1930年代にかけてイタリアで人気を博しました。このカクテルの名前は、イタリアのバーテンダーがアメリカ人観光客の好みに合わせて作ったことから来ています。アメリカ人は当時、軽めで爽やかなカクテルを好んだため、このカクテルが誕生しました。また、アメリカーノは「 ネグローニ 」の前身とも言われており、ジンを追加することでネグローニになります。
ビターで甘味のある風味が特徴です。カンパリの苦味とベルモットの甘味が絶妙に調和し、炭酸水が加わることで爽やかさがプラスされます。カンパリの苦味とベルモットの甘味がバランスよく混ざり合い、複雑でありながら飲みやすい味わいです。
イタリアのカフェ文化を感じさせるクラシックなカクテルで、歴史と伝統を楽しむことができます。
今回ご紹介したレシピは現在のレシピで、元々はカンパリを使わずにビター・ベルモットを使用していました。 ビター・ベルモットの代用としてカンパリを使用し、このレシピが広く浸透していったため、現在ではカンパリをベースとしたレシピが飲まれています。
材料リスト
- このカクテルの〚 道具リスト 〛へ ⇓
世界クラシックカクテル セールスランキング ベスト 50
イギリスの酒類専門誌「 ドリンク・インターナショナル 」が、「 トップセールス( 販売数 ) 」「 トップトレンド( 流行 ) 」をテーマに、厳選された一流のBARなど100店舗からアンケート調査をし、ランキング化して毎年クラシック・カクテルセールスベスト50として発表しています。
- 画像をクリックでランキング総合ページへジャンプします。
ー アメリカーノのランキング歴 ー
- 2025年・20th / 10回目選出・4 down ⇓
- 2024年・16th / 9回目選出・4 up ⇑
- 2023年・20th / 8回目選出・4 down ⇓
- 2022年・16th / 7回目選出・9 up ⇑
- 2021年・25th / 6回目選出・前年同位
- 2020年・25th / 5回目選出・2 down ⇓
- 2019年・23th / 4回目選出・14 up ⇑
- 2018年・37th / 3回目選出・5 down ⇓
- 2017年・32th / 2回目選出・7 up ⇑
- 2016年・39th / 初選出
- 西暦をクリックで年代別ページへジャンプします。
関連のカクテルレシピ リスト








⇒ 画像 / タイトルをクリックでレシピリストページへ
〚 他のカクテル レシピリスト 〛
ベースのお酒・カンパリ
「 カンパリ Campari 」とは、イタリア・ミラノで生まれた様々なハーブやスパイスから作り出されたハーブ & ビター 系のリキュールです。非常に複雑な風味を持ち、最大の特徴は「 サッパリとした苦味 」で、食前酒にとても向いています。
何も知らずに初めて口にする人は、苦手意識を持つかもしれませんが、その苦味がクセになり、そのままロックスタイルで飲む人もいるほどです。見た目は美しい赤色をしていて、その赤色を活かしたカクテルも存在しています。
ハーブの香りに苦味、ほんのりと感じられる甘味がそのままでも飲むことができ、オレンジジュースなどの果汁系、ソーダやトニックウォーターなどの炭酸類と割っても美味しく飲める幅広さも持ち合わせています。
カンパリの歴史
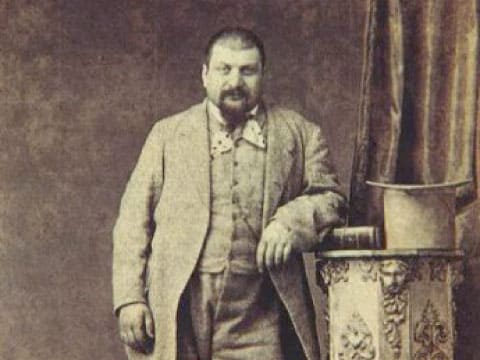
Photo|ガスパーレ・カンパリ|画像引用 Wikipedia
1842年ガスパーレは14歳という若さでトリノにある酒場で見習いとして働き、そこでお酒の知識を身に付けます。
そして地元ノヴァラに帰りカフェ経営を始め、1860年にミラノへ進出。 そこではカフェだけではなく、お酒の販売も同時に行うようになり、そこで自家製リキュールを開発します。
そのリキュールが後の「 カンパリ 」で、当時は「 ビッテル・アルーソ・ドランディア( オランダ風苦味酒 )」と名付け販売していました。
ガスパーレの商売は繁盛し、1867年に近くのアーケード街である ヴィットリオ・エマヌエレ通りで「 カフェ・カンパリ 」を始めます。 そこでカンパリのオリジナルリキュールが人気商品となり、イタリア国王ウンベルト1世、イギリス国王エドワード7世も訪れるという名店となりました。
その後1882年にガスパーレ・カンパリが死去すると、次男である「 ダヴィデ 」が後を継ぎ、製造業が大きく需要を迎えると1904年に自社工場を設立させ、長かった名前を家名である「 カンパリ 」に改名し、フランス、スイスなどの国外に輸出するという販売に力を注ぎます。
カンパリの味わいと製造

はじめの製造から150年たった現在でも変わらない製法で作られています。
キャラウェイ、カルダモン、コリアンダー、オレンジピールなどが主原料だと言われています。
ただ原料は全部で60種類以上あり、その製法や分量など、数少ない製造責任者のみ知られていて、詳細は公開されていません。 正式に判明しているのは、「 水 」、「 アルコール 」のみです。
しかし専門家の分析や官能検査によって、ビター・オレンジ果皮、キャラウェイ、コリアンダー、カルダモン、シナモン、ナツメグなどの約30種類以上のハーブやスパイス類を使用し、それらを100℃でに出した後、中性スピリッツを加えアルコール度数69度で15日間タンクで熟成させます。 これに水、砂糖、アルコール、天然色素を加え、更に1カ月熟成させ濾過をしてボトリングされるということが判明しています。
- カンパリの歴史・主なブランドは ⇒ コチラ
カクテル材料紹介
ー ベルモット Vermouth ー
「 ベルモット Vermouth 」とは、白ワインをベースに、ニガヨモギ など様々なハーブやスパイスなどを使い、スピリッツを加えたフレーバー・ド・ワイン( 強化ワイン )です。
製造方法や原料は全てを公表しておらず、大まかなことしかわかっていません。 原料はハーブの名前がそのまま付いてある通り、キク科ヨモギ属の多年草「 ニガヨモギ 」を主体としています。
ベースのお酒は白ワインで、ニガヨモギをはじめとした、苦レモン、シナモン、コリアンダー、ナツメグ、アンジェリカ、カルダモン、フェンネル、ジュニパーベリー、クローブ、etc…といった20種類以上ものハーブやスパイスを白ワインに漬け込みます。
ベルモットには主にドライとスイートがあり、カクテル材料には欠かせない存在です。
- ドライベルモット・・・辛口のベルモットです。 フランスで生まれたことから「 フレンチ・ベルモット 」と呼ばれています。 ブランドによって異なりますが、色は無色透明から少し黄色が入ったものまであり、スッキリとした味わいとサッパリ感、そしてハーブの香りが特徴で、その特徴からかカクテルの材料に多く使われています。
- スイートベルモット・・・甘口のベルモットです。イタリアで生まれたことから「 イタリアン・ベルモット 」と呼ばれています。色は濃い赤色をしていることや、ロッソと呼ばれたりもしますが、カラメル等の着色をしているのであって、赤ワインの色ではありません。 特徴はやはりハーブの香りとその甘味でしょう。 しっかりとした風味があるので、ドライベルモットよりもロックなどで飲むのに向いているかもしれません。
少しの苦味とハーブなどの香りが特徴で、食前酒としてロックなどそのまま飲まれることが多いですが、カクテルでも多くのレシピに登場します。
- ベルモットの歴史・原料・製法・主なブランドなどは ⇒ コチラ
ビルド & ステア
「 ビルド 」とは「 組み合わせる 」または「 注ぐ 」という意味があり、ステアのように完全に混ぜるのではなく、組み合わせる、もしくはグラスに直接注ぐという目的の際に使います。
「 グラスの中に直接材料を注ぐ 」= ビルド、「 バースプーンで混ぜる 」= ステアと覚えれば間違いはありません。
炭酸系の混ぜ方
炭酸系の材料を使う場合は、早く混ぜたり、回す回数が多いと、炭酸が溢れてこぼれてしまうだけでなく、炭酸ガス自体も抜けてしまうのでゆっくり回すように注意しましょう。
バースプーンやマドラーをグラスの内側に沿って底まで入れます。 グラスに当てたままゆっくりと1回転 ~1.5回転回し、先端のスプーンでゆっくりと氷を持ち上げてゆっくりと下ろします。
混ざりにくい材料の場合は、炭酸以外の材料を入れて一度ステアを行い、炭酸類を入れた後に再度軽くステアするようにします。
バースプーンの使い方

Step 1 = まず左手はグラスの底を押さえます( ドリンクを体温で温めないため )右手はバースプーンを持ちます。( 左利きの人は逆になります )
Step 2 = バースプーンを動画のように中指と薬指の間に挟みます。
Step 3 = 親指と人差し指もバースプーンを挟んで持ちますが、この2本の役割は、落とさないようにするためだけのものなので軽く持ちましょう。
Step 4 = バースプーンの背中をグラスの内側の縁に沿って底へ持っていきます。
Step 5 = 自分の体より向こう側へ回す際は薬指で左回りに押すように持っていき、自分の体側に戻す際は右周りに中指で引き戻すようにバースプーンを移動させます。 この時にバースプーンの背中は常にグラスの外側へ向いています。
この動作の繰り返しになります。 最初は難しいと思うので、大きめのグラスに氷のみで練習すると良いでしょう。 慣れると便利なので、ぜひマスターしてください。
- バースプーンの詳しい使い方は ⇒ コチラ
カクテルのTPO用語
オールデイカクテル All day cocktail

カクテルには様々なシチュエーション向けに考案されたものがあります。
主に食欲を増進させるための食前酒や、デザートのようなテイストの食後向けカクテルであったり、眠る前に飲むカクテル、飲み過ぎた後の迎え酒などと様々です。
そういったシチュエーションなどに無関係であったり、特にこだわりなく考案されたもので、向き不向きが無いカクテルというのがこの「 オール・デイ・カクテル 」です。
プレディナー Pre dinner cocktail
プレディナーカクテル( 食前酒 )とは食事前に飲むお酒のことです。
胃を刺激して消化液の分泌を促進することで、消化器官の負担を軽くする働きがあり、食欲増進の効果があります。
プレディナーの習慣が誕生したのは、18世紀後半から19世紀にかけての間にフランス、イタリアの貴族間から始まったそうです。
プレディナーの特徴はアルコール度数が低いこと、スッキリとした口当たりに爽やかさや爽快感があるものが多いです。

テイストは爽やかな甘味、少しの苦味や酸味が特徴的です。
お酒の種類はスパークリングワインやビールなどの炭酸類が多く見られ、リキュールではアペロールやカンパリといった少し苦味があり、ハーブなどの香りがするリキュールが使われることが多いようです。 カクテルも香り、苦味、爽やかさを使ったものが多く、種類も豊富にあります。
- カクテルを飲むタイミングの名称紹介は ⇒ コチラ
おすすめのグラス
コリンズグラス Collins glass

背が高く細いので倒しやすいという難点がありますが、その細さは炭酸を抜けにくくしているためという最大のメリットがあり、炭酸系のカクテルをつくる時には必ずと言っていいほど使われるグラスです。 容量は270ml ~ 360mlくらいが一般的。
ゴブレット Goblet
ゴブレットとはグラスに土台と足が付いたグラスの事です。
特徴としてはワイングラスのように足が長くないことと、容量が多く入ることで、タンブラーグラスの代わりや、氷をたっぷり使うカクテル、ビール、ドリンクなどで使われ、パフェなどのデザートの器としても使われます。
使い勝手が良く、見た目も上品さと可愛らしさがあり、様々なシチュエーションであったり、お店などで幅広く使われています。

ゴブレットが誕生したのは14世紀だと言われていて、名前はフランス語で、「 Goblet 」と表記します。 元々は「 ゴブレー 」と呼んでいたそうですが、いつの間にか「 ゴブレット 」となったようです。
聖杯にもこのゴブレットが使われており、映画「 ハリーポッター 炎のゴブレット 」でもその名前が使われています。 容量は300ml前後が一般標準サイズ。
タンブラーグラス Tumbler glass

「 タンブラー Tumbler 」の語源は「 倒れるもの 」や「 転ぶもの 」の意味があり、元々獣を狩り、残った角等をくり抜いてコップにし、底が真っ平にはならなかったので、よく倒れていたことからこの名前が付いたそうです。
別名ハイボールグラスとも呼ばれることがあり、主にハイボールスタイルや、ソフトドリンクなどに使われています。 オールドファッションドグラス( ロックグラス )を原型として誕生したとも言われ、オールドファッションドグラスをそのまま縦に長くしたような形をしています。
使い勝手が良く、容量も多く入るため、どの家庭にも必ずいくつかはあるグラスで、用途がおおいためか容量の種類も一番多くあると言っても過言ではないでしょう。
素材もガラス製だけではなく、木製、金属製、陶器、プラスチック製と様々なものがあります。 容量は6オンスの180ml、8オンスの240ml、10オンスの300mlが一般的で、飲食業界では略して6タン、8タン、10タンなどと呼ばれているそうです。
- グラス紹介ページは ⇒ コチラ
道具リスト
- このカクテルの〚 材料リスト 〛へ ⇑












